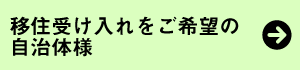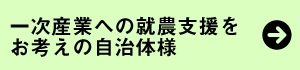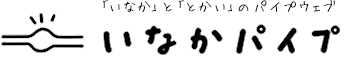カンタロウミミズと出会う
2025年10月に開催した林業体験17期運営中のこと。
林業現場を見学するために移動していた際、現地の方が側溝にいるミミズを教えてくれた。
その名も「カンタロウミミズ」
捕まえてウナギの餌にしたりする、地元民お馴染みのミミズらしい。
指をさされた方を見てみると、てらてら光っている濃い青色、そして明らかにでかい。
良く知っている赤茶色でないので、言われなければミミズと思わない。
 2025年10月林業体験にて
2025年10月林業体験にて
仕事とは言え、通い続けて9年目になろうという高知県れいほく地域の山林であたりまえに生息していたミミズ。
そこそこ山奥にあった祖父母の家でも見たことも聞いたこともないその生き物に衝撃を受け、つい調べたら深みにハマってしまった。せっかく調べたので、まとめついでにブログに残そうかと思った今回。
興味があればお付き合いください。
まずカンタロウという名前にひっかかる
頭の中に浮かんだのは「なんで青い」と「カンタロウ」って寒太郎?貫太郎??
という後者は何ともまぬけな疑問だった。
漢字については現地の方に聞いて見たが、「書いたことがないのでわからない」とのこと。そりゃまあそうか。
ミミズをどこかに書き記す機会なんて滅多にない。
スマホで調べた結果、カンタロウはカンタロウ、漢字でなくカタカナ表記だった。
 参加者みんなで側溝のミミズを探す
参加者みんなで側溝のミミズを探す
ちなみに山林の見学中だった参加者のみんなも、カンタロウミミズに興味津々。
移動中に車内で盛り上がり、カンタロウミミズをそれぞれ調べる時間になった結果、カンタロウミミズは別名で本名(学名)は「シーボルトミミズ」だと判明。
外来種??
かと思ったが、どうやらシーボルトさんが日本で収集して標本をオランダに送ったため、収集者にちなんで命名されたらしい。
さらにちなむと、日本産のミミズに初めて学名が与えられたものがこの「シーボルトミミズ」なのだそうだ。(学名が与えられた日本産ミミズは全部で3種)
シーボルトさんにひっかかる
となると、今度はシーボルトさんって誰??となる。
標本を「オランダ」に送ったとあるから、オランダ人かと思いきや、なんとドイツ人。医師の家系に生まれて、自身も医師だったため、オランダの軍医として当時のオランダ領東インド(参考1)に赴任。
当時鎖国中(参考2)だった日本が唯一貿易を行っていたのが、オランダ。
 オランダ領東インド
オランダ領東インド
そのオランダ領東インド総督に日本研究の希望を述べて認められたことから、長崎の出島のオランダ商館付きの医師として来日したのがそのシーボルトさんというわけ。
しかもシーボルトさん、その後役人の信頼を得て出島内だけでなく長崎市内の日本人の診療も行うようになり、その際に日本の植物などの収集もしていた模様。
日本国民の健康に貢献してくれていた名もなきお医者さん…かと思ったら、その足跡を辿ると日本史に出てくるあのシーボルトさんだったことが判明。
うっすら記憶にはあるが内容までは覚えていない「シーボルト事件」、このシーボルトさんがまさにその人だったのだ!!(ジャジャーン)
(参考1)オランダ領東インドってどこ?
ジャワ島を中心とした現在のインドネシア。17世紀からオランダが進出してオランダ領東インドとして植民地支配していた。
(参考2)鎖国とは何だったのか思い出そう!
鎖国は日本の士農工商という身分制度がキリスト教の布教(人類平等の教え)で崩れてしまうのを恐れた江戸幕府がこれ以上キリスト教が入ってこないよう行った政策で、当時貿易を行っていたポルトガルとスペインの来航を禁止。
その後外国船の来航は長崎のみとなり、長崎の出島ができ、外国とのやり取りは出島でのみ行われるように。
オランダは、キリスト教の布教をしなかったから(中国も同様の理由で)貿易を継続できたわけです。
オランダからは貿易だけでなく鎖国中の日本にはない貴重な外国の情報ももらっていたそうな(オランダ風説書)
シーボルト事件にひっかかる
まさかカンタロウミミズを調べていてこんな歴史と結びつくとは思いもよらず、ちょっと気分が高揚。
もちろん「シーボルト事件」の内容なんて覚えているわけもなく、調べてみることに。
事件のきっかけは江戸幕府11代将軍徳川家斉さんに謁見するためにシーボルトさんが江戸に来たこと。
そこで江戸の学者たちと交友関係になり、その中でも高橋景保氏が保管していた「大日本沿海輿地全図」に関心を持ち、また高橋景保氏はシーボルトさんが持っていた「世界周航記」(参考)に関心を持ったことから、「大日本沿海輿地全図」の写しと「世界周航記」の交換が成立、しかしここに大きな問題が・・・。
なぜなら大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず)は、江戸時代後期、伊能忠敬が中心となって作製した日本全土の実測地図で、あまりに詳細な地図のため国防上の問題から流布を禁止していたから。
任期を終えてオランダに帰る直前、シーボルトさんの積荷の中に件の地図があることが発覚し、シーボルトさんは軟禁されて家宅捜索と地図の没収、そして国外追放・再渡航禁止の処分を受けることになったそうな。
もちろん、高橋景保氏含む日本側の関係者も多く処分されたとのこと。
これが「シーボルト事件」だった。
(参考)「世界周航記」
ロシア海軍提督であり探検家のクルーゼンシュテルンがロシア船最初の世界周航を実現し、その詳細を「世界周航記」に記録した。途中、日本の長崎にも来航している(通商交渉は幕府に拒否られる)。
 大日本沿海輿地全図一部(ディジタル貴重書展)
大日本沿海輿地全図一部(ディジタル貴重書展)
カンタロウミミズに戻る
さて、どんどん話が逸れていきそうなので一旦カンタロウミミズに戻ることにする。
そしてせっかく調べたので特徴を簡単に記載してみる。
そもそもカンタロウミミズは日本最大のミミズのひとつで、西日本の山林に生息する日本固有種らしい。
日本固有種!
なのにここで初対面とは・・・。
「日本最大のミミズのひとつ」という説明なので、あといくつあるか調べてみたが、【日本最大】【日本固有種】で何度調べてもシーボルトミミズしか検索結果にひっかからないので断念。
ちなみに西日本と言っても屋久島や沖縄には見られないという。
なぜか?は、もう調べない。
ウナギの餌によく使われるのは、その大きさと動きがウナギを引き寄せるのに効果的だからだそう。
どうやら地表に這っていることが多いようで簡単に捕まえられ、中でも雨が降った翌日などはよく地表にいるらしく、採集するのならそのあたりが狙い目だとか。
特に「山の斜面や落ち葉が溜まったU字側溝を掘るのが効果的」とのことで、、、今回の発見はまさにここ。
ウナギがよく食いつくのと、見つけやすいということから、ウナギの餌に定着したのかな。
ちょっと興味深かったのは、カンタロウミミズは季節によって【生息場所を変える】ということ。
夏には尾根筋から斜面にかけて広く散らばって生活、冬になると谷底に集まって越冬。
なので、春には谷から斜面へ、秋には斜面から谷底へと大規模な移動があり、林道の側溝や斜面にカンタロウミミズが集まる光景が「カンタロウの大移動」として話題になることもある、とのこと。
今のところ、れいほく地域でこの「カンタロウの大移動」が話題になったことはないけれど。
私の知らないところで大移動は粛々と行われているのかも、しれない。
カンタロウミミズ以外の別名
当然気になったのが、シーボルトミミズ→カンタロウミミズなら、ほかにも別名があるのでは?ってこと。
で、探したら、出るわ出るわ。
・山ミミズ (九州、四国、中国地方)
・ドバミミズ (愛媛県伊方町)
・ヤマミミズ・ヤマヘビ (九州)
・カブラタ・カブラッチョ(紀伊半島)
・カミサンミミズ (奈良県吉野宮滝あたり)
・カブラタ、カブラタイ、カルバタ(和歌山県那智勝浦)
・アオミミズ、オーミミズ、ヤマノミミズ、ヤマミミズ(三重県鈴鹿市・亀山市)
ヤマミミズ、アオミミズは理解できるけどカブラタあたりはどうしてそうなったのか見当もつかない。
そしてこれらを調べた学者さんに感謝、である。
カンタロウミミズの青い色の原因
ここで!?
って思うかもしれないけれど、ミミズの青い色にも言及を。
もっと早く疑問に思っていたけれど、とにかくシーボルトさんに引っ張られてしまっての、ここ。
 ヘモシアニンとは!?
ヘモシアニンとは!?
調べた結果を並べても、いまいち意味がわからないのでそのまま書くと、、、カンタロウミミズの青色の由来は、酸素の運搬に銅系色素(ヘモシアニン)を活用しているから。
なるほど、そういうことか!!ってならないけど仕方ない。
イカやタコの血が青いのと同じく、ヘモグロビンではなくヘモシアニンが酸素を運んでいるから、が答えだった。
まとめ
まだまだ未知なる生き物は身近にあるものだと感じる。
新たな生き物、言葉、出会い、を通り過ぎるのは簡単だけれど、少しひっかかってみるだけで、新しい扉がまたひとつ開く。
わかっていても見過ごすもので、なるべく見逃さないよう丁寧に生きていきたいものです。
ここまで読んでくれた方、お付き合いいただきありがとうございました。
ちょっと気になるその後のシーボルト
シーボルト事件はわかったけど、その後のシーボルトさんが気になったので追記。
事件内容では触れられてないけれど、国外追放になる前になんとシーボルトさん、日本女性と結婚して娘を設けておられまして。事件から30年後に日蘭修好通商条約が結ばれて再渡航禁止処分が解除になると、再来日し、その際に日本人初の産科医になった娘とも再会。
それだけでなく、問題となった地図はひそかに持ち出していて(諸説あり)、1840年にオランダで日本地図を発行しちゃっている。
それだけでなく持ち帰った資料を基に日本についての研究書「日本」、「日本動物誌」「日本植物誌」なども出版しちゃっている。
ただでは起きない人だった。